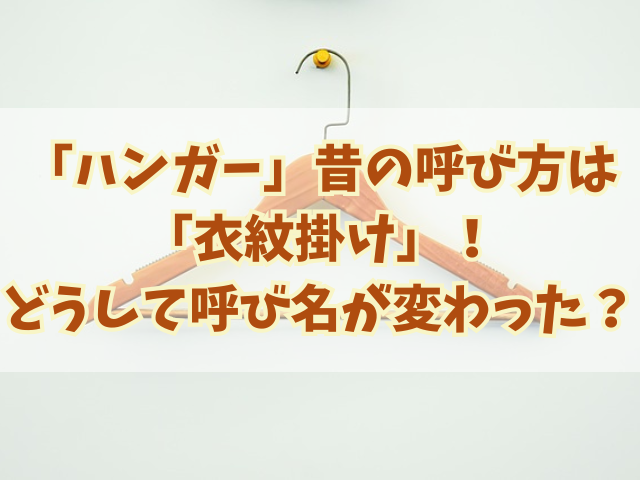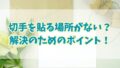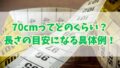クローゼットや洗濯物干しで日常的に使われる「ハンガー」。
しかし、かつて日本ではこれを「衣紋掛け(えもんかけ)」と呼んでいました。
時代の流れとともに変化した呼び名について、本記事では、「ハンガー」という言葉の歴史やその背景、なぜ「衣紋掛け」と呼ばれていたのかを深掘りしながら、日本の暮らしとファッションの変化をたどります。
ハンガーの歴史と昔の呼び方
「衣紋掛け」とは?昔の言い方の背景
「衣紋掛け」は、和服を着用する日本で使われてきた伝統的な用語で、衣類を丁寧に保管するための道具として長い歴史を持っています。
主に着物や羽織を型崩れさせずに吊るすことを目的としています。
多くは木製の棒状で、壁に取り付けるタイプや、自立式のスタンド型などが存在し、家庭内だけでなく旅館や呉服店などでも使われていました。
衣紋掛けは、衣類を単なる物としてではなく、生活の一部として扱っていた時代がありました。
ハンガーはいつから使われ始めたのか?
現在一般的に使われている洋服用ハンガーは、19世紀後半の欧米で登場しました。
当時、洋服の保管や展示の利便性を高めるために、金属製や木製の肩の形を模した道具が開発。
これらはシャツやジャケットを吊るすことに特化しており、衣類の型崩れを防ぐための工夫が施されていました。
日本では明治時代に入って洋装が広がるにつれて徐々に輸入・使用され始め、昭和時代には家庭でも広く普及するようになります。
洋服箪笥と共に、ハンガーは普遍的な存在になっていきました。
ハンガーと衣紋掛けの違いを解説
衣紋掛けは、和装特有の平面構造に合わせて作られており、通気性や型崩れ防止といった観点から工夫されています。
対してハンガーは、肩のラインに合わせて立体的に設計されており、スーツやシャツといった洋装のシルエットを保つことを目的としています。
素材も木・金属・プラスチックなど多様化し、滑り止め加工や肩パッド付きなど機能面でも工夫されています。
両者は形状も用途も異なり、それぞれの衣服の特徴と必要性を反映しており、時代や生活様式の違いが道具に表れている好例です。
ハンガーの発明者とそのこと

ハンガーを発明した人物とは?
現在の形に近い針金ハンガーを発明したのは1903年、アメリカ・ミシガン州に住んでいたアルバート・パークハウスといわれています。
歴史に名を刻んだ発明者の背景
パークハウスは、ジャクソン・ミシガン州にあるテンペル・ワイヤー&ノヴェルティ社の社員であり、日常的に針金を扱う職場に勤務していました。
ある日、職場で従業員用のコート掛けが不足していたため、即興で自ら針金を曲げて肩の形を模した器具を作り、コートを掛けたのがハンガー誕生の瞬間といわれています。
その機能性と手軽さが評判となり、同僚たちからも好評を得たことで、会社がその形を基にした製品の製造に乗り出しました。
ハンガーの発明がもたらしたこと
ハンガーの発明により、衣類を型崩れさせずに保管・展示できるようになり、家庭だけでなくアパレル業界やクリーニング業界、ホテル産業などでも不可欠な存在となりました。
特にアパレルショップでは、商品を見栄え良く陳列するためにハンガーの形状や素材に工夫が加えられ、ブランディングの一環としても使われています。
また、家庭での収納方法も大きく変化し、クローゼットや押し入れをより効率的に活用する工夫が進みました。
ハンガーは単なる道具にとどまらず、暮らしの中での「衣類との向き合い方」そのものに関わる存在となったのです。
日本におけるハンガーの変遷

着物とハンガーの関係
日本では長らく和服が主流であり、衣紋掛けは着物の保管に欠かせない存在でした。
着物を長期間美しい状態で保つために不可欠な道具として親しまれてきました。
また、衣紋掛けには収納という実用性に加え、着物を扱う所作や心構えまでも含まれた側面を担っていました。
旅館や茶道教室、舞台の裏方などでは、今もなお衣紋掛けが重要な役割を果たしています。
洋服が普及する中での言葉の変化
明治維新以降、西洋の流入とともに洋服の着用が増加し、生活様式が大きく様変わりしました。
「ハンガー」という言葉もそのまま輸入され、当初は限られた層にしか使われていなかったものの、洋服の普及とともに一般家庭にも使われるようになっていきます。
結果として「衣紋掛け」は次第に使われなくなり、現在では主に和装や伝統の場面でのみ用いられるようになりました。
この言葉の変化は、単なる語彙の移り変わりというよりも、日本人の生活様式や衣服に対する変化の流れからきているでしょう。
日本独自のハンガーの進化
日本では住宅事情や収納スペースの限界から、省スペース化や収納効率化のニーズが高まり、それに応える形で折りたたみ式、回転式、滑り止め付き、さらには多機能型のハンガーなど、独自の改良が加えられてきました。
これにより、限られたスペースでも効率的に衣類を管理できるようになり、特に都市部での生活にフィットした形となっています。
また、着物専用のハンガーも現代風にリデザインされており、木製で装飾性の高いものや、素材に竹や漆を使った高級仕様のものなど、実用性と美しさを兼ね備えた製品も登場しています。
こうした日本独自の工夫は、日々の暮らしに寄り添いながら、伝統と現代の融合を体現しています。
まとめ
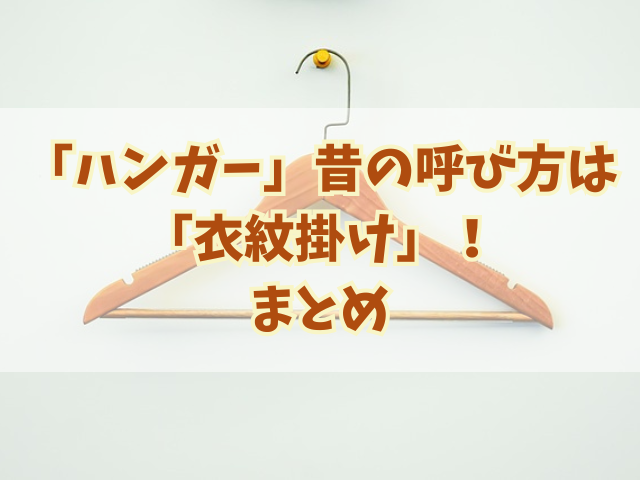
「ハンガー」という言葉は、ただの外からきた言葉ではなく、日本の衣生活の変化が分かるものです。
かつての「衣紋掛け」という呼び名に込められた丁寧な暮らしの姿勢を忘れず、今の便利な生活と共に大切に受け継いでいきたいものです。